dodaチャレンジ 断られた理由とは?難しいと感じた体験談と対処法を詳しく解説

dodaチャレンジで断られた!?断られた理由や断られる人の特徴について解説します
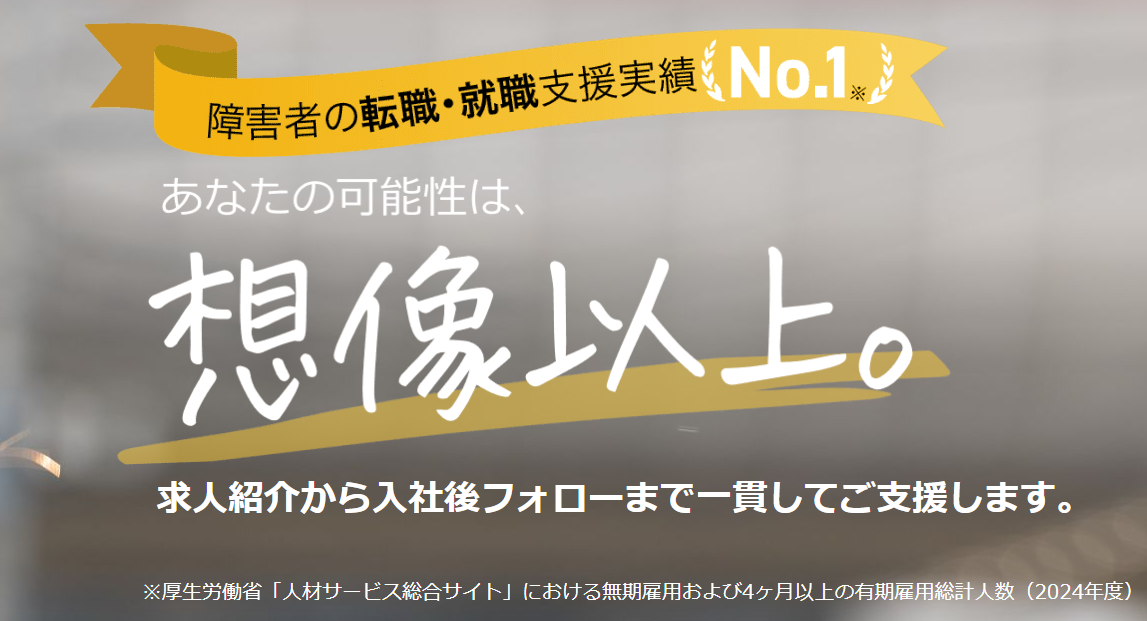
dodaチャレンジは、障がい者向けの就職支援サービスとして信頼性が高く、多くの方に利用されていますが、すべての方が必ずサービスを受けられるとは限りません。
実際に「断られた」「サポート対象外だった」という声もあります。
ここでは、なぜdodaチャレンジで断られることがあるのか、よくある理由や該当する人の特徴についてわかりやすく解説します。
断られる理由1・紹介できる求人が見つからない
dodaチャレンジでは、利用者の希望条件に合った求人を紹介することを重視していますが、条件が限定的すぎると、マッチする求人が見つからない場合があります。
希望条件が厳しすぎる(在宅勤務限定、フルフレックス、年収500万円以上など)
在宅勤務や高年収、フレックス制度などを希望する方は多いものの、こうした条件は障がい者雇用枠ではまだ数が少なく、希望に合う求人が出にくいのが現実です。
条件を柔軟に調整することで、紹介の幅が広がる可能性があります。
希望職種や業種が限られすぎている(クリエイティブ系、アート系など専門職など)
専門性の高い職種は、求人そのものが少ないうえ、障がい者雇用枠での募集はさらに限られています。
そのため、こうした職種に強くこだわる場合は、dodaチャレンジ以外のサービスや、自主応募との併用を検討するのも一つの手です。
勤務地が限定的(地方で求人自体が少ない)
地方や人口の少ないエリアでは、障がい者雇用の求人が都市部に比べて少ない傾向があります。
そのため、在住地域によっては紹介できる求人がなく、結果的に断られてしまうケースがあります。
断られる理由2・サポート対象外と判断される場合
dodaチャレンジは、基本的に「就職・転職したい」という明確な意志を持った方を対象にしています。
そのため、支援が難しいと判断された場合には、別の支援機関の利用を勧められることがあります。
障がい者手帳を持っていない場合(障がい者雇用枠での求人紹介は、原則手帳が必要)
dodaチャレンジでは障がい者雇用枠の求人を扱っているため、原則として障がい者手帳の提示が求められます。
診断書のみで利用可能な場合もありますが、求人によっては紹介が難しくなることがあります。
長期間のブランクがあって、職務経験がほとんどない場合
過去に働いた経験が極端に少ない場合、すぐに企業への紹介が難しいと判断されることがあります。
そのような場合は、まずは就労移行支援などで社会復帰をサポートするプログラムの案内を受けることもあります。
状が不安定で、就労が難しいと判断される場合(まずは就労移行支援を案内されることがある)
就労の意欲があっても、健康状態や生活リズムが安定していない場合には、継続的な勤務が難しいと判断されることもあります。
その際には、dodaチャレンジから就労移行支援や医療的な支援機関を紹介されるケースもあります。
dodaチャレンジを利用する際には、希望条件を柔軟にすることや、就労への準備段階を見直すことも大切です。
断られたからといって諦めず、自分に合ったサポート機関を探すことが次の一歩につながります。
断られる理由3・面談での印象・準備不足が影響する場合
dodaチャレンジでは、最初の面談が求人紹介の重要なステップになります。
そのため、面談時の準備や受け答えが不十分だと、サポートが進まないケースがあります。
障がい内容や配慮事項が説明できない
「どのような配慮が必要か」を自分の言葉で説明できない場合、企業への紹介が難しくなります。
面談では、就労に必要な配慮や体調面の注意点を具体的に伝えることが求められます。
どんな仕事をしたいか、ビジョンが曖昧
「何でもいい」「特に決まっていない」という回答では、マッチする求人が提案しづらくなります。
得意なことや興味のある職種を事前に考えておくと、面談がスムーズに進みます。
職務経歴がうまく伝わらない
過去の経験やスキルがはっきり伝わらないと、アドバイザーが強みを把握できません。
簡単なメモでもよいので、これまでの仕事や得意なことを整理しておくと印象が良くなります。
断られる理由4・地方エリアやリモート希望で求人が少ない
全国対応とはいえ、地域によっては求人の選択肢が限られているのが現実です。
地方在住(特に北海道・東北・四国・九州など)
地方では企業の数が少なく、障がい者雇用枠の求人も限定的です。
そのため、希望する職種や条件に合う求人が見つからず、紹介ができないケースがあります。
完全在宅勤務のみを希望している場合(dodaチャレンジは全国対応ではあるが地方によっては求人がかなり限定される)
在宅勤務の求人は人気が高く、競争率も高いため、完全リモートのみを条件にすると紹介できる求人が非常に限られてしまいます。
フルリモートだけでなく、週何日かの出社も視野に入れると可能性が広がります。
断られる理由5・登録情報に不備・虚偽がある場合
登録時の情報は、求人紹介や企業とのやり取りの基礎となるため、正確性が非常に重要です。
手帳未取得なのに「取得済み」と記載してしまった
障がい者雇用枠の求人には原則として手帳が必要となるため、虚偽の記載があると信頼を損ね、紹介ができなくなります。
働ける状況ではないのに、無理に登録してしまった
通院中や体調が不安定な時期など、実際の就労が難しい場合には、登録前に一度立ち止まって体調を整えることが大切です。
dodaチャレンジでは、必要に応じて就労移行支援の利用も案内されます。
職歴や経歴に偽りがある場合
経歴詐称があった場合、企業との信頼関係にも影響を与えます。
過去の職歴やスキルは事実に基づいて正直に伝えることが必要です。
断られる理由6・企業側から断られるケースも「dodaチャレンジで断られた」と感じる
アドバイザーからのサポートが続いていても、実際の選考結果によっては企業側から不採用となることがあります。
不採用は企業の選考基準によるもの
dodaチャレンジの紹介を受けて応募しても、企業側が求めるスキルや人物像と一致しなければ、不採用になることはあります。
この場合は「dodaチャレンジで断られた」と誤解しがちですが、あくまで企業の判断によるものです。
このように、dodaチャレンジでの「断られた」というケースにはさまざまな背景があります。
自分に合った働き方を実現するためにも、条件や希望の整理、丁寧な情報提供が大切です。
必要であれば他のサービスや支援機関と併用しながら、長期的な視点でキャリアを考えていくのが良いでしょう。
dodaチャレンジで断られた人の体験談/どうして断られたのか口コミや体験談を調査しました
dodaチャレンジは、障がい者の方が安心して就職・転職できるように手厚いサポートを提供していますが、中には「サービスを利用できなかった」「求人を紹介してもらえなかった」という体験をした方もいます。
ここでは、実際にdodaチャレンジで断られてしまった方の声をもとに、どんな理由でそうなったのか、背景や改善のヒントを解説していきます。
体験談1・障がい者手帳は持っていましたが、これまでの職歴は軽作業の派遣だけ。PCスキルもタイピング程度しかなく、特に資格もありません。紹介できる求人がないと言われてしまいました
体験談2・継続就労できる状態が確認できないため、まずは就労移行支援などで安定した就労訓練を』と言われてしまいました。
体験談3・精神疾患で長期療養していたため、10年以上のブランクがありました。dodaチャレンジに相談したものの、『ブランクが長く、就労経験が直近にないため、まずは体調安定と職業訓練を優先しましょう』と提案されました
体験談4・四国の田舎町に住んでいて、製造や軽作業ではなく、在宅でのライターやデザインの仕事を希望していました。dodaチャレンジからは『ご希望に沿う求人はご紹介できません』といわれました
体験談5・これまでアルバイトや短期派遣での経験ばかりで、正社員経験はゼロ。dodaチャレンジに登録したら、『現時点では正社員求人の紹介は難しいです』と言われました
体験談6・子育て中なので、完全在宅で週3勤務、時短勤務、かつ事務職で年収300万円以上という条件を出しました。『ご希望条件のすべてを満たす求人は現状ご紹介が難しいです』と言われ、紹介を断られました
体験談7・精神障がい(うつ病)の診断を受けていますが、障がい者手帳はまだ取得していませんでした。dodaチャレンジに登録を試みたところ、『障がい者手帳がない場合は求人紹介が難しい』と言われました
体験談8・長年、軽作業をしてきたけど、体調を考えて在宅のITエンジニア職に挑戦したいと思い、dodaチャレンジに相談しました。『未経験からエンジニア職はご紹介が難しいです』と言われ、求人は紹介されませんでした
体験談9・身体障がいで通勤も困難な状況で、週5フルタイムは無理。短時間の在宅勤務を希望しましたが、『現在ご紹介できる求人がありません』と断られました
体験談10・前職は中堅企業の一般職だったけど、今回は障がい者雇用で管理職や年収600万以上を希望しました。dodaチャレンジでは『ご紹介可能な求人は現在ありません』と言われました
dodaチャレンジで断られたときの対処法について詳しく紹介します
dodaチャレンジで「紹介できる求人がない」と言われたり、「サポートの対象外」と判断されてしまった場合でも、それが終わりではありません。
状況に応じた準備や工夫を重ねることで、次のチャンスをつかむことは十分可能です。
ここでは、スキル不足やブランクが理由でサポートが難しいとされた方のために、具体的な対処法をご紹介します。
スキル不足・職歴不足で断られたとき(職歴が浅い、軽作業や短期バイトの経験しかない、PCスキルに自信がないなど)の対処法について
dodaチャレンジでは、職務経験やスキルにある程度の基準が求められるため、実績やアピール材料が少ない場合には、まずは基礎力を身につける準備が必要です。
ハローワークの職業訓練を利用する/ 無料または低額でPCスキル(Word・Excel・データ入力など)が学べる
ハローワークでは、就職支援の一環として「公共職業訓練」や「求職者支援訓練」を実施しています。
基本的なパソコン操作から実務的なスキルまで、幅広く学べる講座が用意されており、受講料は無料または格安です。
修了後には修了証が出るため、職務経歴の少ない方でもスキルを証明できます。
就労移行支援を活用する/実践的なビジネススキル、ビジネスマナー、メンタルサポートも受けられる
就労移行支援事業所では、実際の職場を想定した訓練や、職場適応のためのサポートを受けることができます。
通所しながら生活リズムを整え、働く自信をつけられるため、未経験の方やスキルに不安がある方にとっては非常に有効です。
資格を取る/MOS(Microsoft Office Specialist)や日商簿記3級があると、求人紹介の幅が広がる
短期間で取得でき、かつ実務で役立つ資格を取ることで、選べる求人の幅が広がります。
特にMOSや簿記3級は事務系職種で高く評価されるため、スキルに不安がある方の強い味方になります。
ブランクが長すぎてサポート対象外になったとき(働くことへの不安が強い、数年以上の離職や療養期間があるなど)の対処法について
長期のブランクがある場合は、まずは「働く準備」を整えることが重要です。
生活リズムや心身の安定、職場環境への適応力などを一つずつ整えていきましょう。
就労移行支援を利用して就労訓練をする/毎日通所することで生活リズムを整え、安定した就労実績を作れる
毎日の通所を通じて、通勤や作業に慣れる訓練ができる就労移行支援は、ブランクが長い方にとって非常に効果的です。
利用期間中に企業実習や職場見学の機会もあり、実践的なスキルを身につけられます。
短時間のバイトや在宅ワークで「実績」を作る/週1〜2の短時間勤務から始めて、「継続勤務できる」証明をつくる
体力や体調に不安がある場合は、まずは無理のない範囲で短時間の仕事から始めてみることが有効です。
週数日の在宅ワークや軽作業でも、「継続して働ける」ことを証明できれば、再度dodaチャレンジへの登録時に好印象につながります。
実習やトライアル雇用に参加する/企業実習での実績を積むと、再登録時にアピール材料になる
就労移行支援や自治体のプログラムでは、企業実習やトライアル雇用が実施されている場合があります。
こうした取り組みに参加し、実績を積むことで、履歴書に書ける経験が増え、再チャレンジ時の説得力が高まります。
このように、dodaチャレンジで断られてしまった場合でも、その後の行動次第で再びサポートを受けられる可能性は十分にあります。
焦らず、自分のペースで就労準備を整えていくことが、次のステップへの確かな一歩となります。
地方在住で求人紹介がなかったとき(通勤できる距離に求人が少ない、フルリモート勤務を希望しているなど)の対処法について
地方に住んでいると、特に障がい者雇用枠での求人は都市部に比べて選択肢が限られる傾向があります。
dodaチャレンジで求人紹介が難しかった場合でも、他の手段をうまく活用することでチャンスを広げることができます。
在宅勤務OKの求人を探す/他の障がい者専門エージェント(atGP在宅ワーク、サーナ、ミラトレ)を併用
完全在宅勤務の求人を得意とする障がい者向けエージェントを活用することで、dodaチャレンジでは見つからなかった求人に出会える可能性があります。
特にatGP在宅ワークは在宅専門の求人が豊富です。
クラウドソーシングで実績を作る/ランサーズ、クラウドワークスなどでライティングやデータ入力の仕事を開始
在宅で始められる小さな仕事でも、継続的に取り組めば立派な職務実績になります。
将来的に再びdodaチャレンジに登録する際のアピールポイントにもなるので、まずは一歩を踏み出してみることが大切です。
地域の障がい者就労支援センターやハローワークに相談する/地元密着型の求人情報が得られる場合がある
地元企業とのつながりが強い支援機関では、Web上に出ていない求人情報や企業実習の案内が得られることもあります。
地元で働きたい方には特におすすめの選択肢です。
希望条件が厳しすぎて紹介を断られたとき(完全在宅・週3勤務・年収◯万円など、条件が多いなど)の対処法について
希望条件が多すぎると、求人が見つからないことがあります。
条件を見直して現実的なラインを探ることが重要です。
条件に優先順位をつける/「絶対譲れない条件」と「できれば希望」を切り分ける
すべての条件を満たす求人を探すのは難しいため、まずは譲れない条件と、妥協できる部分を整理してアドバイザーに伝えると、マッチングの可能性が高まります。
譲歩できる条件はアドバイザーに再提示する/ 勤務時間、出社頻度、勤務地を柔軟に見直す
「週5は無理だけど週4なら可能」「完全在宅希望だけど月1出社なら可能」など、現実的な範囲で調整することで、紹介できる求人の幅が広がります。
段階的にキャリアアップする戦略を立てる/最初は条件を緩めてスタート→スキルUPして理想の働き方を目指す
まずは実績づくりを目的に働き始め、経験を積んだ後に希望の条件に近づけていく方針も有効です。
現状の選択肢を活かしながら長期的な視点で動くことで、理想の働き方に近づけます。
手帳未取得・障がい区分で断られたとき(障がい者手帳がない、精神障がいや発達障がいで手帳取得が難航している、支援区分が違うなど)の対処法について
手帳の有無や障がいの認定状況によっては、障がい者雇用枠の求人紹介ができない場合もありますが、対処方法はいくつかあります。
主治医や自治体に手帳申請を相談する/ 精神障がい・発達障がいも条件が合えば取得できる
医師の診断と必要な書類がそろえば、精神障がいや発達障がいの方でも手帳の取得が可能です。
まずは主治医に相談し、申請の可否を確認してみましょう。
就労移行支援やハローワークで「手帳なしOK求人」を探す/一般枠での就職活動や、就労移行後にdodaチャレンジに戻る
一部の就労支援機関や一般求人には、手帳なしでも応募できるものがあります。
段階的に経験を積み、後日dodaチャレンジに再登録するという流れも現実的です。
医師と相談して、体調管理や治療を優先する/手帳取得後に再度登録・相談する
体調が不安定な段階での無理な就職活動は逆効果になることもあります。
まずは治療や生活リズムの安定を目指し、手帳取得後に改めてチャレンジすることで、より良いマッチングにつながります。
その他の対処法/dodaチャレンジ以外のサービスを利用する
dodaチャレンジ以外にも、障がい者の就職をサポートするサービスは多数あります。
atGP、サーナ、LITALICOワークス、ココルポート、地域の就労支援センターなど、それぞれに特色があるため、自分に合った支援機関を探すことが重要です。
どの方法も「今は難しい」という状況を一歩ずつ前進させるための手段です。
自分にできることから始めて、再びdodaチャレンジや他の就職支援サービスでチャンスをつかむ準備をしていきましょう。
dodaチャレンジで断られた!?精神障害や発達障害だと紹介は難しいのかについて解説します
dodaチャレンジは、すべての障がい種別に対応している障がい者向けの転職支援サービスですが、実際に「精神障害」や「発達障害」の方が紹介を受けにくいという声も一部で見られます。
ここでは、その理由や背景を、身体障がいの就職状況と比較しながら詳しくご紹介します。
身体障害者手帳の人の就職事情について
身体障がいを持つ方は、障がいの内容が比較的「視覚的に理解しやすい」ため、企業側にとっても配慮がしやすく、結果的に採用につながるケースが多くなっています。
障害の等級が低い場合は就職がしやすい
軽度の身体障がい(たとえば指の欠損や軽度の聴力障がいなど)の場合は、業務への支障が少ないと判断され、一般職に近い形での採用がされることも珍しくありません。
身体障がいのある人は、障がいの内容が「見えやすい」ことから、企業側も配慮しやすく採用しやすい傾向にある
目に見える障がいであれば、企業側もどのような対応が必要かがイメージしやすいため、安心して雇用しやすいという声があります。
これは、企業にとって「対応すべき範囲が明確」というメリットがあるためです。
企業側が合理的配慮が明確にしやすい(例:バリアフリー化、業務制限など)から、企業も安心して採用できる
たとえば車椅子利用の方にはスロープ設置、聴覚障がいの方には筆談やチャット対応など、具体的な対応策が取れることもあり、受け入れ態勢が整えやすいという点が身体障がいの就職における強みです。
上肢・下肢の障がいで通勤・作業に制約があると求人が限られる
一方で、歩行が困難、立ち作業ができないなど身体機能に制限がある場合は、通勤や業務内容によっては求人の選択肢が狭まることもあります。
その場合、在宅勤務や配慮のある職場を探す必要が出てきます。
コミュニケーションに問題がない場合は一般職種への採用も多い
対人業務や電話対応など、ビジネスに必要な基本的なコミュニケーション能力に問題がなければ、営業事務や総務などのポジションでの採用が進みやすくなります。
PC業務・事務職は特に求人が多い
身体的な負担が少ない事務職は、障がい者雇用においてもニーズが高く、パソコンが使える方であれば採用のチャンスも広がります。
特にExcelやWordのスキルがあると、求人紹介の幅も広がりやすくなります。
このように、身体障がいのある方は企業とのマッチングが比較的しやすい背景がありますが、dodaチャレンジでは精神・発達障がいにも専門のアドバイザーが対応しており、丁寧なヒアリングを通じて最適な職場を見つける支援が行われています。
次回は精神障害・発達障害の方の事情や対応についてご紹介していきます。
精神障害者保健福祉手帳の人の就職事情について
精神障害のある方が就職を目指す際には、症状の安定や職場への適応力が特に重視されます。
dodaチャレンジでも、精神障害者保健福祉手帳を所持している方への支援を行っていますが、就職の難易度やサポートの方向性には独自の特徴があります。
症状の安定性や職場での継続勤務のしやすさが重視される
企業側が最も気にするのは「継続して働けるかどうか」です。
短期間での退職が続いている場合や、通院頻度が高く勤務に支障が出る場合は、企業側の不安材料になることがあります。
そのため、安定して働ける状態であることが、就職活動の大きなカギとなります。
見えにくい障がいなので、企業が「採用後の対応」に不安を持ちやすいのが現実
精神障がいは外見では判断できないことから、企業側が「どのように配慮すれば良いのか」が分かりにくく、不安を感じやすい傾向があります。
そのため、入社前から適切な情報共有と説明ができるかどうかが、採用の可否を分けるポイントになります。
採用面接での配慮事項の伝え方がとても大切!
「どのような配慮があれば働きやすいか」を具体的に説明できることが重要です。
たとえば、「静かな場所で集中しやすい」「定型業務であればスムーズに対応できる」といった形で、自身の強みと必要な配慮を明確に伝えることで、企業側も安心して採用に踏み切りやすくなります。
療育手帳(知的障害者手帳)の人の就職事情について
知的障がいをお持ちの方が就職を目指す場合、療育手帳の区分(A判定・B判定)によって進路が大きく異なります。
dodaチャレンジではB判定の方の一般就労支援を行っているケースが多く、A判定の場合は他の支援機関と連携した対応が検討されます。
療育手帳の区分(A判定 or B判定)によって、就労の選択肢が変わる
療育手帳は、知的障がいの程度によってA判定(重度)とB判定(中軽度)に分かれており、それに応じて一般就労が現実的かどうかが変わってきます。
A判定(重度)の場合、一般就労は難しく、福祉的就労(就労継続支援B型)が中心
重度の知的障がいがある場合は、企業での就労が難しいことが多く、福祉施設での軽作業や就労訓練が中心になります。
そのため、dodaチャレンジでは対応できないケースもあり、地域の就労支援センターや相談支援専門員との連携が重要です。
B判定(中軽度)の場合、一般就労も視野に入りやすい
軽度~中度の知的障がいがある方で、ある程度の作業理解や指示への対応が可能であれば、一般企業での就職も十分に可能です。
dodaチャレンジでも事務補助や軽作業系の求人紹介を受けられるケースが多く、就労意欲と安定した生活リズムがあれば積極的にサポートが受けられます。
このように、障がいの種類や特性によって就職活動の方向性や支援内容は異なりますが、それぞれに適した支援機関や対処法が用意されています。
自分の特性を理解し、必要な配慮や準備を整えていくことで、無理のない形での就職を目指すことができます。
障害の種類と就職難易度について
障がい者の就職は、障がいの種類や程度によって難易度が大きく変わることがあります。
dodaチャレンジなどの就職支援サービスを利用する際も、自分の状況に合った準備と戦略が重要です。
以下の表では、各種手帳の区分ごとに「就職のしやすさ」「向いている職種」「就職活動でのポイント」についてまとめています。
| 手帳の種類 | 就職のしやすさ | 就職しやすい職種 | 難易度のポイント |
| 身体障害者手帳(軽度〜中度) | ★★★★★★ | 一般事務・IT系・経理・カスタマーサポート | 配慮事項が明確で採用企業が多い |
| 身体障害者手帳(重度) | ★★ | 軽作業・在宅勤務 | 通勤や作業負担によって求人が限定 |
| 精神障害者保健福祉手帳 | ★★ | 事務補助・データ入力・清掃・在宅ワーク | 症状安定と継続勤務が評価されやすい |
| 療育手帳(B判定) | ★★★★ | 軽作業・事務補助・福祉施設内作業 | 指導・サポート体制が整った環境で定着しやすい |
| 療育手帳(A判定) | ★★ | 福祉的就労(A型・B型) | 一般就労は難しく、福祉就労が中心になる場合が多い |
このように、身体障がいのうち軽度から中度に該当する方は、配慮内容が明確に伝えられることから企業側も受け入れやすく、就職のチャンスが広がりやすい傾向があります。
一方で、精神障がいや知的障がい(A判定など)の場合は、継続勤務の可否や職場へのサポート体制が重要視され、紹介可能な求人が限定されることもあります。
就職の成功には、自分の障がい特性を正しく理解し、必要な支援や配慮を的確に伝える準備が欠かせません。
dodaチャレンジでは、それぞれの状況に合わせて適切な求人紹介やアドバイスを行ってくれるため、不安がある場合はまず一度相談してみることをおすすめします。
障害者雇用枠と一般雇用枠の違いについて
就職・転職活動をするうえで、障がいのある方には「障害者雇用枠」と「一般雇用枠」の二つの選択肢があります。
それぞれの枠には特徴やメリット・デメリットがあるため、自分の状況や希望に合わせて適切に選ぶことが重要です。
以下では、それぞれの雇用枠の特徴を分かりやすくご紹介します。
障害者雇用枠の特徴1・企業が法律に基づき設定している雇用枠
障害者雇用枠は、障害者雇用促進法により企業が義務として設けている枠です。
この枠での採用は、障がいを持つ方の就職をサポートすることを目的とした制度に基づいており、企業も制度に則った対応を行う義務があります。
障害者雇用枠の特徴2・障害者雇用促進法により、民間企業は従業員の2.5%以上(2024年4月〜引き上げ)を障がい者として雇用するルールがある
2024年4月以降は、法定雇用率が2.5%に引き上げられ、企業にはより積極的な障がい者雇用が求められています。
そのため、障害者雇用枠の求人は年々増加傾向にあり、就職の機会も広がっています。
障害者雇用枠の特徴3・障害をオープンにし配慮事項を明確に伝えた上で雇用される
この枠での雇用は「オープン就労」が前提となっており、自身の障がいや配慮してほしい点を事前に企業へ開示します。
これにより、職場での業務内容や勤務時間などに合理的配慮を受けることができ、安心して働ける環境が整いやすくなります。
一般雇用枠の特徴1・障害の有無を問わず、すべての応募者が同じ土俵で競う採用枠
一般雇用枠は、障がいの有無に関係なく誰でも応募できる採用枠です。
企業はスキルや経験、人物面を重視して選考を行うため、障がいのある方も健常者と同等の条件で評価されます。
一般雇用枠の特徴2・障害を開示するかは本人の自由(オープン就労 or クローズ就労)
この枠では障がいを開示する義務はなく、自分の判断で「伝える」「伝えない」を選べます。
ただし、就労上配慮が必要な場合に障がいを開示しないと、企業側が適切な対応を取れないこともあるため、慎重な判断が求められます。
一般雇用枠の特徴3・基本的に配慮や特別な措置はないのが前提
一般雇用枠では、「健常者と同じように働けること」が前提とされているため、業務内容や勤務時間に特別な配慮が期待しにくい側面があります。
そのため、障がいによる体調や制限に不安がある方は、事前に環境や業務内容をよく確認し、必要であれば障害者雇用枠も視野に入れることが安心です。
年代別の障害者雇用率について/年代によって採用の難しさは違うのか
障がい者雇用においては、年齢によって採用されやすさや求人の傾向が変わることがあります。
特に企業が求めるスキルや経験、勤務形態に対する柔軟性などは年代によって異なるため、それぞれの年代での就職戦略を立てることが大切です。
以下では、厚生労働省の「障害者雇用状況報告(2023年版)」を元に、年代別の構成比と主な就業状況をまとめました。
障害者雇用状況報告(2023年版)を元に紹介します
| 年代 | 割合(障害者全体の構成比) | 主な就業状況 |
| 20代 | 約20~25% | 初めての就職 or 転職が中心。
未経験OKの求人も多い |
| 30代 | 約25~30% | 安定就労を目指す転職が多い。
経験者採用が増える |
| 40代 | 約20~25% | 職歴次第で幅が広がるが、未経験は厳しめ |
| 50代 | 約10~15% | 雇用枠は減るが、特定業務や経験者枠で採用あり |
| 60代 | 約5% | 嘱託・再雇用・短時間勤務が中心 |
20代では「ポテンシャル採用」が主流で、未経験や短期経験でも応募できる求人が多いため、初めての就職やキャリアのスタートに適しています。
就労移行支援や職業訓練と組み合わせながらスキルを磨くことで、選択肢がさらに広がります。
30代になると、これまでの職務経験を活かして「安定就労」を目指す方が多くなります。
企業側も即戦力としての期待を高めるため、実績や専門性をアピールできるかがポイントになります。
40代では、過去の経歴に応じて幅広い職種が選べる一方で、未経験職への転職は難易度が高くなります。
スキルの棚卸しやキャリアの見直しが大切になります。
50代になると、求人自体が少なくなる傾向がありますが、経験を活かした専門的な業務や契約社員、時短勤務など柔軟な働き方での採用もあります。
60代では再雇用や短時間勤務、定年後の継続雇用などが中心になります。
体力や勤務日数への配慮が求められるため、希望条件に合った職場を探すことがカギになります。
このように、年代ごとに採用状況や企業のニーズは異なりますが、それぞれの年代に合った準備や工夫をすることで、より良いマッチングにつながります。
dodaチャレンジなどの就職支援サービスを活用して、自分に合った働き方を見つけていきましょう。
若年層(20〜30代)の雇用率は高く、求人数も多い
20代〜30代の若年層は、障がい者雇用においても特に需要が高く、企業側も将来的な成長や長期的な雇用を見据えて積極的に採用する傾向があります。
未経験OKの求人も多く、スキルや職歴が少ない場合でも、ポテンシャルを重視して採用されるケースが目立ちます。
また、dodaチャレンジをはじめとする就職支援サービスも、この年代に対して豊富な求人を保有しています。
40代以降は「スキル・経験」がないと厳しくなる
40代以上になると、企業は即戦力としてのスキルや実務経験を重視する傾向が強くなります。
そのため、職歴が乏しい場合やブランクが長い場合は、紹介される求人が限られてくることもあります。
dodaチャレンジでは、職務経歴や希望に応じて職業訓練や就労移行支援との併用を提案するケースもあり、再就職への準備を整えることが重要です。
50代以上は「短時間勤務」「特定業務」などに限られることが多い
50代を超えると、体力面や業務範囲の制限を考慮して、短時間勤務や定型的な業務、サポート業務が中心となる求人が増えます。
また、年齢とともに雇用機会そのものが減少するため、地域のハローワークや福祉サービスを併用しながら、地元密着型の就労支援を活用することも一つの方法です。
dodaチャレンジなどの就活エージェントのサービスに年齢制限はある?
dodaチャレンジでは公式に年齢制限を設けていませんが、実際には紹介できる求人の多くが「50代前半まで」を想定した内容であることが多くなっています。
そのため、年齢が高い場合は紹介可能な求人が限られてくることもあり、他の支援機関の併用が推奨されます。
年齢制限はないが 実質的には「50代前半まで」がメインターゲット層
特に企業の求人要件では、将来的なキャリア形成や定着を見据えた30〜40代を中心とする傾向があるため、50代以降の求職者には職種や働き方の選択肢が絞られることがあります。
ただし、これに該当する方でも、専門性や経験を活かせる業務では採用の可能性が十分にあります。
ハローワーク障がい者窓口や障がい者職業センター(独立行政法人)も併用するとよい
年齢や体調などの条件に合わせた支援を受けたい場合は、dodaチャレンジだけでなく、ハローワークの障がい者窓口や、障がい者職業センターといった公的機関を併用するのが有効です。
福祉的就労や実習、訓練制度など幅広いサポートを受けながら、自分に合った働き方を段階的に探すことができます。
このように、年齢に応じた就職活動の工夫と支援機関の併用が、障がいのある方のキャリア形成には欠かせないポイントとなります。
自分に合った方法を見つけることが、長く働き続けるための第一歩となります。
dodaチャレンジで断られたときの対処法についてよくある質問
dodaチャレンジは障がいのある方に特化した就職・転職支援サービスですが、時には「求人を紹介されなかった」「面談後に連絡がなかった」など、うまくいかないこともあります。
ここでは、よくある疑問や不安への回答をまとめました。
dodaチャレンジの口コミや評判について教えてください
dodaチャレンジは「サポートが丁寧」「希望条件に合った求人を紹介してくれた」という高評価の口コミが多くあります。
一方で「連絡が多い」「希望に合う求人が見つからなかった」という声もあり、相性や希望条件によって印象は異なるようです。
関連ページ:dodaチャレンジの口コミや評判はどう?障害者雇用に特化したサービスの特徴やメリット・デメリットをわかりやすく解説
dodaチャレンジの求人で断られてしまったらどうすれば良いですか?
求人が紹介されなかった場合は、希望条件の見直しやスキルアップ、他の支援機関の併用を検討するのが効果的です。
就労移行支援や職業訓練を通じて再チャレンジすることで、次のチャンスを広げることができます。
関連ページ:dodaチャレンジ 断られた理由とは?難しいと感じた体験談と対処法を詳しく解説
dodaチャレンジで面談後に連絡なしの理由について教えてください
連絡が来ない場合、多くは求人の選定に時間がかかっているケースがほとんどです。
不安な場合は、アドバイザーに自分から確認の連絡を入れてみましょう。
タイミングによっては、求人の調整や企業とのやり取りが進行中の場合もあります。
関連ページ:dodaチャレンジ 連絡なしの理由は?面談・求人・内定に関するケース別の原因と連絡が来ないときの対処法を解説します
dodaチャレンジの面談の流れや聞かれることなどについて教えてください
面談では、これまでの職歴、スキル、希望の職種、勤務形態、障がいに関する配慮事項などが丁寧にヒアリングされます。
準備が不安な方でも、履歴書や職務経歴書の作成支援もあるので安心です。
関連ページ:dodaチャレンジ 面談の流れを徹底解説|内定までのステップや準備・注意点・効果的な対策方法とは
dodaチャレンジとはどのようなサービスですか?特徴について詳しく教えてください
dodaチャレンジは、障がい者雇用に特化した転職支援サービスで、全国対応、全障がい種別に対応しています。
求人紹介、書類添削、模擬面接、内定後のフォローまで一貫してサポートが受けられるのが特徴です。
キャリアアップ支援にも力を入れており、継続的に働ける職場を一緒に探してくれます。
障がい者手帳を持っていないのですが、dodaチャレンジのサービスは利用できますか?
障がい者手帳がない場合でも、医師の診断書などにより相談や登録が可能な場合があります。
ただし、障がい者雇用枠の求人紹介には、原則として手帳が必要なため、利用できるサービスや求人の幅が限定されることがあります。
手帳の取得を検討している場合は、主治医や自治体に相談してみると良いでしょう。
dodaチャレンジに登録できない障害はありますか?
基本的にdodaチャレンジは、身体障害・精神障害・知的障害・発達障害など、すべての障がいに対応しています。
ただし、就労の意欲や体調が安定していない場合、もしくは就労継続が難しいと判断された場合には、他の支援機関(就労移行支援など)を勧められることもあります。
また、障害者手帳が未取得の場合は、紹介できる求人が制限されることがあります。
dodaチャレンジの退会(登録解除)方法について教えてください
退会を希望する場合は、担当のキャリアアドバイザーに連絡し、退会の意思を伝えることで手続きを進められます。
その後、ヒアリングや確認を経てアカウント情報の削除が行われます。
進行中の求人紹介や面談がある場合は、事前にキャンセルの連絡が必要です。
アカウントを完全に削除すると、情報は復元できなくなるため、必要な情報はあらかじめ保存しておくと安心です。
dodaチャレンジのキャリアカウンセリングはどこで受けられますか?
dodaチャレンジのキャリアカウンセリングは、オンライン(ビデオ通話・電話)で全国どこからでも受けられます。
一部エリアでは対面面談も実施されることがありますが、基本的にはリモートでの対応が中心となっています。
自宅から相談できるため、通院や移動が難しい方でも安心して利用できます。
dodaチャレンジの登録には年齢制限がありますか?
公式には明確な年齢制限はありませんが、実質的には「18歳以上~50代前半」がメインの対象層とされています。
それ以降の年齢でも登録は可能ですが、紹介可能な求人が限られることがあります。
シニア層の場合は、ハローワークや地域の就労支援機関との併用を検討するとよいでしょう。
離職中ですがdodaチャレンジのサービスを利用できますか?
はい、離職中でも問題なく利用できます。
dodaチャレンジでは「今すぐ働きたい」方から「まずは相談から始めたい」という方まで幅広く対応しています。
ブランクがある方も歓迎されており、再就職に向けた準備段階から丁寧にサポートしてくれます。
学生ですがdodaチャレンジのサービスを利用できますか?
基本的にはdodaチャレンジは中途採用を前提としたサービスのため、新卒・学生向けのサポートは限定的です。
ただし、障がい者手帳を持ち、卒業後すぐの就職を希望している場合や、就活に関する事前相談を希望する場合には、登録・面談が可能なケースもあります。
状況によっては、新卒向け就活エージェントやハローワーク新卒支援窓口の併用もおすすめです。
参照:よくある質問(dodaチャレンジ)
dodaチャレンジは断られない?その他の障がい者就職サービスと比較
障がい者の就職を支援するサービスは多数ありますが、その中でも「dodaチャレンジ」は全国対応かつ全障害種別に対応しており、求人の質やサポート体制が整っていることで注目されています。
しかし、すべての利用希望者が必ずしも支援対象となるわけではなく、状況によっては「断られた」と感じるケースもあるのが実情です。
ここでは、dodaチャレンジとその他の代表的な障がい者就職支援サービスを比較しながら、それぞれの特長を整理してご紹介します。
| 就職サービス名 | 求人数 | 対応地域 | 対応障害 |
| dodaチャレンジ | 1,500 | 全国 | 全ての障害 |
| アットジーピー(atGP) | 1,500 | 全国 | 全ての障害 |
| マイナビパートナーズ紹介 | 350 | 全国 | 全ての障害 |
| LITALICOワークス | 4,400 | 全国 | 全ての障害 |
| 就労移行支援・ミラトレ | 非公開 | 全国 | 全ての障害 |
| ランスタッドチャレンジ | 260 | 東京、神奈川、千葉、埼玉、大阪 | 全ての障害 |
| Neuro Dive | 非公開 | 全国 | 全ての障害 |
| Cocorport | 非公開 | 首都圏、関西、東海、福岡 | 全ての障害 |
dodaチャレンジは、全国対応かつ全障害に対応している点で、利用のしやすさという面では非常に優れています。
特に、企業とのマッチング精度やアフターフォローの充実度が評価されており、職場定着率の高さにもつながっています。
一方で、LITALICOワークスのように求人数が多く、就労移行支援機能を持つサービスでは、働く準備段階から手厚いサポートが受けられるため、スキルや就労経験に不安がある方には向いています。
また、ミラトレやCocorportといった地域密着型の支援機関も、それぞれの地域特性に合わせた支援が受けられる点で魅力的です。
「dodaチャレンジで断られた」と感じた方は、希望条件や就労経験によって他のサービスとの併用を検討するのもおすすめです。
サービスごとの特徴を理解し、自分に合った支援を受けることが、就職成功への近道となります。
dodaチャレンジで断られた!?断られた理由と対処法/難しいと感じた体験談まとめ
dodaチャレンジは、障がい者専門の転職支援サービスとして多くの方に利用されていますが、中には「求人を紹介してもらえなかった」「登録を断られた」と感じる方もいます。
その背景には、スキル不足や就労ブランク、条件が厳しすぎることなど、さまざまな要因があります。
たとえば、軽作業や短期の職歴しかない、PCスキルや資格が乏しいといった場合は、紹介できる求人が限られるため、サポートが難しくなることもあります。
また、精神障害や発達障害の方の場合、症状や必要な配慮をうまく伝えられなかったことが原因で、求人紹介に進めなかったという体験もあります。
ほかにも「完全在宅・週3日・高年収希望」など条件が厳しい場合は、マッチングが成立しにくくなります。
こうした状況に対しては、希望条件を見直したり、ハローワークの職業訓練や就労移行支援を活用したりして、スキルや就労実績を積むことが有効です。
MOSや簿記3級などの資格取得も、事務系求人などに応募する際の強みになります。
また、dodaチャレンジ以外にも、atGP、LITALICOワークス、Cocorportなど多様な支援機関があり、特性に応じたサポートを受けられます。
dodaチャレンジで断られたことは「自分に合った就職方法を見直すきっかけ」として前向きにとらえ、他の選択肢や支援策と併用しながら次のステップに進んでいくことが大切です。
焦らず一歩ずつ準備を重ねれば、自分に合った働き方にきっと出会えます。
関連ページ:dodaチャレンジの口コミや評判はどう?障害者雇用に特化したサービスの特徴やメリット・デメリットをわかりやすく解説
